
|
SHIBUYA COSMIC BASKING 直枝政広 スペシャル鼎談 Vol.2 ゲスト:吉田ヨウヘイ、西田修大(吉田ヨウヘイgroup) 構成・執筆:松永良平 取材協力:BYG(渋谷) ──カーネーションの3ヶ月連続対バン・ライヴ・シリーズ《SHIBUYA COSMIC BASKING 2018 spring》、 第二弾の相手となる吉田ヨウヘイgroup(以下YYG)から、吉田ヨウヘイ、西田修大のお二人に来ていただきました。 西田くんは今回、昨年11月以来ですが、カーネーションにもギターで参加します。直枝さんはYYGの新作『ar』(2017年11月)にもコメントを寄せていました。でも、ここがつながったというのは、両者のファンとして見ても、かなり新鮮ですよね。 直枝 まず、西田(修大)くんとは、MUSEMENTのライヴ(《夜のミューズメント》2017年4月19日、渋谷 CLUB QUATTRO)で共演をしていて、そのときに話をしたらいろいろと意気投合したんですよ。普通、音楽の現場にいると、むしろ音楽の話から逃げて、よけいな話をしたがるんだけど、彼はちゃんとギターの プレイとか機材とか、音楽をどういうふうにとらえてるのかということを常にぶつけてくるタイプだった。そこにとても好感を持ったし、ぼくらもちゃんとしなきゃな、と思いました(笑) 西田 聞きたいことがたくさんあったんで、いろいろ質問しました。 直枝 ぼくの使ってるアンプは、デラックス・リバーブっていうヴィンテージなんですけど、その意味をわかってくれるっていうのがうれしかった。 西田 MUSEMENTのリハーサルでご一緒したときに、直枝さんがセッティングしてギターを弾いたら、今まで聴いたことない感じのすごい音がしたんですよ。休憩になったらすぐに直枝さんに「この音、どういうことなのか教えてもらっていいですか?」って聞きました(笑)。そしたら、初めて会ったよくわからないやつなのに、「ちょっと弾いてみていいよ」って言ってくれて。そのときに、今まで都市伝説だと思ってたような音が実在するということがわかったんです。だから、去年、自分が一番音色として影響を受けたのは、直枝さんのそのときの音でしたね。ギター始めたときに読む雑誌とかで「理想の音作り」として書かれていることなんですけど、正直、自分の体験的には、そんなことはありえないと思っていたんです。それを直枝さんがやってたことを実際に目と耳で体験した。それで、音作りに対する自分の考えも変わりましたね。すぐに吉田さんにも電話して伝えたと思います。 吉田 そうだったね。直後にあたらしいアンプ買ってたよね。 西田 ぼくもアンプを音作りの軸にしたくなったんです。そういうところで直枝さんの影響は本当にでかかった。本当はデラリバを探したんですけど。 直枝 ぼくのは63年製の、一番最初のモデルなんです。Phishのトレイが使ってるやつ。 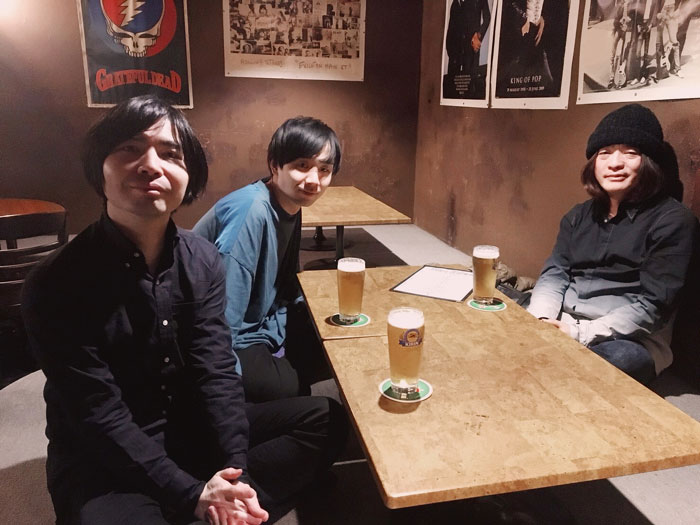 ──しかし、西田くんが吉田くんに感動を電話で伝えたっていうのは、いい話ですね。 吉田 メンバーみんなとそのあと会ったときも、「直枝さんがめちゃくちゃ感じよくて、かっこよかった」っていう話をしてましたね(笑) 西田 なんていうか、音も人柄も想像以上だったんですよ。全部が「そうだったらいいなと思うけどそんなことないよな、と思ってたことが本当だった」って感じで、それがぼくにはめちゃくちゃ新鮮で大事だったんです。 ──YYGとして、年上の世代のバンドと交わることは、わりとめずらしいですよね。 吉田 去年末にスピッツのイベント《新木場サンセット 2017》(2017年12月13、14日、新木場STUDIO COAST。YYGは13日に出演)に呼んでもらったりしましたけど、それが初めてくらいですかね。あとは、年上でお付き合いがあるのは、大谷(能生)さん。大谷さんと知り合って、ご自宅に泊めてもらったときに、「カーネーション大好きなんだよね」って話を聞きました。 直枝 能生と会わないと、ちょっと調子わるくなるくらいぼくも彼のことが好きなんだよね(笑)YYGの音楽性もそうだけど、彼らのリスナーとしての幅もすばらしいとぼくは思ってるんです。特に、今の一番あたらしいジャズというものへも理解がある。そこも、いいなと思う理由のひとつなんですよ。そのへんのリスナーの経験というか、どういう風に今にたどり着いたのかも聴いておきたかったんですけど、まずはリスナーとしてはどういう始まりだったんですか? 吉田 ギターを始めた中学生のときは最初はメタルばかり聴いてました。高校生のときにファッション雑誌『Smart』のCMで、浅野忠信さんが出演しているバックではっぴいえんどの「あしたてんきになあれ」が流れて、それをクラスメートが「すごくいいから」って聴かせてくれたんですよ。その時期はちょうどビートルズも聴き始めた時期で、はっぴいえんどを聴いて「あ、日本でもこんなかっこよくて、好きな感じのバンドがあるんだ」と思ってて、そこからは古めのロックをすごく好きになっていきました。ソフト・マシーンとか聴いてましたね。 直枝 カンタベリー系も聴いている音ですよね。 吉田 そういう感じでロックやフォークに興味を持っていって、大学のサークルで後輩だった西田に出会うんです。今よりぼくの音楽はもっとフォーク色が強かったし、西田はバトルズとかレッド・ホット・チリ・ペッパーズとか、演奏がかっちりできる人が好きだったので、何でぼくの曲に興味を持ったのかはよくわからないんですけど(笑)。でも、西田と一緒にバンドをやることになったときに、自分の好きな音楽の魅力をぼくと作る音楽に入れようって提案してきたんですよ。じゃあ、その折衷点を取るにはどうしたらいいんだろう、というのが2人の音楽を作る過程にはありましたね。そのときに、西田が「フォーク的なものがリズムを溜めたりしないとできないと思うのは間違いだ」って言ったのが印象に残ってます。でも、当時の彼はフォークとかをそんなに好きじゃなかったので、「本当かよ?」とも思ってましたけど(笑) 西田 今でもおれはそう思ってるよ(笑) 吉田 おれも今はそう思う。リズムをすごく正確にした上にフォーク的なうねりを重ねる、そういうことが自分たちのやりたい流れとしてあるんですよ。そういう音楽性に至ったのは、そもそも好きな音楽が違うのに一緒にやろうとしたという部分がでかかったんです。でも、“フォーキーだけどリズムが正確”というフォーマットは、やってみたらいろんな音楽性を取り入れやすかったんですよ。 直枝 そうか! グリッドを意識するということが、そもそもすでに現代的なんですよ。そこが個性なんですね。でも、歌う言葉の上では感情って揺れるよね。そことグリッド上の演奏におもしろい距離感ができていく。ぼくが聴いておもしろいと思うのはそこだよね。 西田 そういう意味では、ぼくと吉田さんが、もともとどっちがどういう考え方だったのかも最近わからなくなってきてるのが、いいなと思ってますね。 吉田 「もっとここはグリッドより溜めよう」って思うのが、自分でもいやだと感じることもあるもんな。 西田 逆におれが溜めたいときもある。 吉田 お互いにジャッジが反転してるときがあります。 直枝 そうなんだ、おもしろい! ──そういう、タイトなのか、ルーズなのかを判断していくときに、どちらかに完全に寄ってしまわない。そこも、今のジャズを摂取してるセンスがすごく役立ってるんじゃないかと思うんですよね。あと、フォーキーなものとエレクトリックなものが突然変異的に融合してるという意味では、リチャード・トンプソンとサンディ・デニーがいた頃のフェアポート・コンヴェンションを思い出す部分もぼくはあります。じゃあ逆に聞きますけど、吉田くんたちの世代には、カーネーションはどういうバンドに見えてたんですか? 吉田 本当はぼくら、もともとカーネーションを若いときから聴いてておかしくないタイプの音楽好きだと思うんです。だけど、大学ではハードロックっぽいサークルにいたせいなのか、あんまり先輩から教わったりしてなかった。ぼくは『レコード・コレクターズ』とかをよく読んでたので、そこで直枝さんのお名前は目にしてはいました。ただ、カーネーションというバンド名からして、もっと軽い感じでおしゃれな音楽性だと勝手に思っちゃってたんですよ。そこからちゃんと興味を持つようになったきっかけは、ぼくがフランク・ザッパが好きで、和久井光司さんがザッパについて書いた本を読んでたときに、直枝さんと和久井さんとの対談を読んだことでした。「あ、こんなにめちゃくちゃマニアな人がカーネーションやってるんだ」と認識して、そこからちょっとずつ聴き出して。今回、ぼくらの新作にコメントをいただいたときも、カーネーションの新作『Suburban Baroque』を聴いて、めちゃくちゃいいなと思ってました。今までで一番好きなアルバムです。 直枝 ありがとう。うれしいな。 吉田 王道で変というか、いつまで経ってもちゃんとあたらしいものを作る人たちとして見られるし、演奏力も音楽のよさに生きてる、そういうポジションでロールモデルになるバンドって今までウィルコしかいなかったんです。でも、カーネーションがそういうバンドなんだな、って認識しました。 直枝 ぼくらが意識していたこともまさにそこなんですよ。ウィルコという存在がとても大きい。彼らはぼくより歳下なんですけど、非常にお手本になるものを持っている。彼らは、古典を愛している。彼らが生まれた時代を愛している。そして今を愛している。すべてを肯定していく力を彼らは持っているし、何も否定してないんだよね。アメリカどっぷりのカントリー野郎じゃなく、ジャーマン・ロックにも通じる硬質な音楽性もある、その懐の広さが最高だよね。吉田くんたちが意識しているのがウィルコなんだろうということも何となくわかってはいた。音の質感とか、西田くんのギター・スタイルもウィルコのネルス・クラインみたいにとんがった部分を持ってるしね。 吉田 ありがとうございます。 直枝 あと、(YYGは)日本語を大切にしてる。歌詞カードを読みたくなるバンドってめずらしいですよ。キーボードの彼女(reddam)の書いた歌詞もいい。たぶん、みんなで歌詞の話とかもいろいろするんだろうなあ、って勝手な想像もしてました。抽象的な言葉の使い方もあるけど、そっちに寄ってしまってない。あくまでひとりの人間がすっと立ってるのが見える。ぼくはそこがすごい好き。 吉田 うれしいです。 西田 reddamにも言ってやんないと。めっちゃ喜ぶと思う。あいつがぼくの身近では一番カーネーションが好きなんですよ。いろいろカーネーションのことも遡って教えてもらってるんです。 ──最近のYYGは順風満帆のように見えるかもしれないですけど、じつは2016年には数ヶ月間、活動休止していた期間もあって。『ar』は、メンバー・チェンジを経ての再始動盤でもあります。そういう意味では、さっき話に出ていたウィルコがそうだったように、カーネーションも長いキャリアの中でメンバー・チェンジや作風の変化などいくつかのターニングポイントを経てきているんですよね。変化しつつも一貫した部分もあって。そういうタフなバンドであるということも、下の世代から頼もしく見えるところなのかなと思うんです。 直枝 YYGがどういう経緯でメンバー・チェンジがあったのかとかぼくにはわからないけど、体勢を変えなきゃいけない時期ってバンドにとってすごくきつくないですか? 吉田 そうですね。体の一部が持って行かれて、組織として弱くなるというか。 直枝 体調とか大丈夫でした? 吉田 一年くらい経ってから自分を振り返ると、「あのときのおれ、おかしかったな」と思うようなことはありますね。 直枝 なるよね。それはすごくわかるな。ぼくらもずっと続けてるようでいて、メンバーの脱退もあったし、何もなかった一年とか結構あるから。その間にいろんなことを考えたり、曲は作っていたりして、2年後くらいに実を結んだりするんだけどね。でも、バンドをやってくってそういうことでもある。特に一気に社会性を自分のバンドが持ち始めるときって、必ずそういう大きい変化があるんですよ。それはチャンスなんです。「(YYGは)今回それを越えたんだな」って新作を聴きながら思ってました。 吉田 うれしいです。 直枝 とっても抜けのいいアルバムだったから。よくぞここに着地したよね。すごいな、努力したんだなと思って、感動しました。 ──さっき、この2人(吉田と西田)は大学時代からの知り合いだという話がありましたけど、リレーションがとてもいい、というのも、側から見ててもわかるんですよね。 直枝 そうだよね。2人でいろいろ話すの? 西田 この10年単位で見たら、一番話してるんじゃない? 吉田 西田とは、バンドの中で幼なじみ的ノリが唯一ありますね。年齢差は5歳あるんですけど。 直枝 おもしろいね。ぼくも矢部(浩志)くんとは5歳離れてるからね。その差がちょうどいいのかもね。お互いが持ってるものを客観的に見ることができたり、影響受けたり、意見が違ってても一緒にやれたりできるしね。 西田 抑えてるというわけでもないですけど、最近は、ガチでやりあうとかはそんなにないですけどね。まあ、制作をするときはまたあるんでしょうけど。 直枝 だろうね、あの音だもの(笑)。だけど、あんなにアイデアが溢れてて、音数も多いバンドなのに、しっかりギターがハマるんだよね。今って、ポストロックやヒップホップ的な音作りが多い時代で、ギターが邪魔に思われることもあるでしょ。でも、そういったスタイルの中でギターを大切にしてるというのがいいよね。 西田 そこはぼくもよく考えるんです。理由のひとつは、吉田さんがギターの音がすごく好きなことだと思うんです。それこそアルバムを録るときも、「もうちょっとヴァイみたいになんないかな?」とか言われて。 直枝 スティーヴ・ヴァイ? 西田 そうです(笑)。今そういうこと、あんまりみんな言わないじゃないですか。吉田さんって、すげえギターが好きで、要求もしっかりするし、こっちにまかせてもくれる。そもそも吉田さん自身もギターを弾くということもある。あと、直枝さんがおっしゃったように「時代的には今ギターはちょっと斜陽だけど」という感覚も自分たちには、たぶんあるんですよ。でも、逆に言えば、自分たちが戦うときには「ギター、かっこいいでしょ」っていうのは転じて武器になると思ってます。 直枝 そうだね。 西田 だから、それをどこかで意識してる部分はすごくあると思いますね。 吉田 そこはカーネーションへの憧れともすごく関係してます。リード・ギターがいる編成なのに、ヴォーカルの直枝さんもギターがすごく好きで、めちゃうまいっていうのがわかるから。あと、カーネーションを聴いてて、すごくうれしくなる部分は、ベースラインとかが「この人が弾くから、こういうスペースをあければ絶対いいプレーがくる」みたいに考えてコンポーズしてるのがわかる気がするんです。ぼくと西田はそういうのが好きなんです。自分たちも、曲を書くときにそういうことを考えてるんで、カーネーションがやってることがビシバシ伝わってきて。例えば「It's A Beautiful Day」も、ベースラインへの考え方が違ったら、あんな曲にならないですよね。 直枝 基本的に作曲するとき同時にベースのラインが見えてくるんですよ。 西田 ファクターとして曲と一緒に浮かぶということですよね。おれらのギターにも感覚的にそういう部分はあるじゃない? 吉田 西田のコンポーズもぼくと近くなってきてる部分があるんですよ。「絶対、西田くんが作ったよね?」って聞かれたギターのフレーズをぼくが作ってたり、今回西田が作曲した曲の歌のラインでも「おれよりおれっぽい!」って思うようなところもあったり。 直枝 ビートルズみたいだね(笑)。「ここはポールだろ?」と思ったところがジョンだったりする。でもYYGには、ひとつの世界があるよね。カーネーションは、ぼくの世界、矢部くんの世界、棚谷くんの世界とかがあってできてる感じだったけど、YYGはみんなでひとつのものを作ってる感覚だよね。 西田 でも、メンバーそれぞれの世界があるということにも、逆に憧れますけどね。その形態自体にロマンがある。ぼくらが次に見たい世界の理想のひとつではあります。 吉田 そうだね。 直枝 2枚組みたいなの、作ったら? 吉田 やばいですね。 西田 やばいね(笑) 直枝 シンプルな部分と、構築された部分の両方出したらいいんですよ。そしたら素っ裸な感じの吉田くんが出て来てる曲もある、みたいなね(笑) 西田 そのアイデア、大事にしましょう。おもしろいですね。 ──YYGを最初に知ったときは、ギターロックというより、チェンバーロックという感覚で紹介されていたんですよね。ダーティー・プロジェクターズ的というか。編成にもフルートやファゴットがいたり。 直枝 ザッパが好きなんだろうな、とは思ってましたね。イアン・アンダーウッドがいた時期の『アンクル・ミート』(1968年)とか、『バーント・ウィニー・サンドウィッチ』(1969年)とかさ。 吉田 好きですね。最近また聴いてたんですよ。練習中に西田と「ザッパのYouTubeのこの映像、正式な音源ではこういうアレンジじゃないけど、こういうのやろう」とか話したりしてました(笑) 直枝 いやあ、でもすごいな。自分が好きだと思ってる音楽に誰しも近づきたいと思うじゃないですか。でも、(YYGは)確実にそれを越えて行こうとしてるし、いつの間にか独創性に繋がってる感じがあるんですよ。コピーじゃない。もっと混沌としたおもしろみがあるんだよね。すごく頼もしいし、物の作り方としてタフだなと思うんですよ。 ──カーネーションも、3人になり、2人になり、とバンドとしての単位が変化していく中で、ライヴは固定サポートを迎えてやっていくのかと思いきや、ライヴごとに違ったりした。そこもおもしろいですよね。 直枝 そうなんですよ。人のスケジュールで音が変わるという珍しいパターン。おれと大田くんは、わりとひょうひょうとそこを泳ぎ抜いてますね。それが今のバンドのスタイルというか、レコーディングでも「スタジオに誰かを呼ぶことがアレンジなんだ」と思うようになったし、みんなもそれをわかって来てくれるようになった。なので、「みんなで作るカーネーション」になってますね(笑) 吉田 そのモードへの切り替えって、どういうきっかけだったんですか? 直枝 3人になったのが2002年。矢部くんが抜けたのが2008年。2人になって『Velvet Velvet』(2009年)というアルバムを出して、そのあたりまでは自分の中のシンガー・ソングライター的な姿勢を出せば続けていけるものだろうと思ってた。あとは編成を超えていくアレンジを作るという発想でスタジオ作を作る。そういうやり方を取ってみたんですよ。ただ、今はシンガー・ソングライターというよりはプロデューサー的な発想に変わってきてて、もうちょっと客観的かな。もちろん作るときは「歌う自分」というのはいるんだけど、「どういうアルバムになるのか」みたいな全体のことばかり考えてる。全体的に考えるというか、できてみないとわからない曖昧なところも多いんだけど、その代わり、今のぼくはそこを楽しんでますね。 西田 でも、直枝さんは本当にそれを楽しんでますよね。すごく印象的だったのは、ぼくをカーネーションのギターに最初に誘っていただいた去年の11月のリハで、「今回は急なオファーなので定番の曲も多いんですが、せっかく一緒にやるんだから、さらなるスケールアップを目論みましょう」って言ってくださって。それにぼくはすごくびっくりしたんです。初めて参加するぼくに、「まあ気楽にやんなよ」とか「しっかりやってくれ」くらいの言葉はありえても、「一緒にスケールアップを目論もう」は、自分のなかでは予想してなかった。もっと責任か、無責任かのどちらかを求められると思ってたのに、「一緒にこれ楽しもうぜ」ってスタンスをいきなり出してくれるとは。だから、本当に直枝さんは、不確定なものや、これから起こることを楽しもうとしてるんだなと思いました。 直枝 そうですね。それがないと頼む上でも失礼だと思ってて。たとえば、キーボードでときどき参加してくれてる渡辺シュンスケくんがふともらした一言があって。「直枝さん、言葉では言わないようでいて、“おまえ、わかってんだろうな”ってすげえ言ってる」って(笑)。いや、そんな風には思ってないんだけど、そう勝手に解釈してくれるのもすごくうれしいんですよ。「ぼくらの庭で自由に思うことをやってもらえれば」という意味のことを常に言ってます。それはカーネーションが2人になって、いろんなこだわりがなくなってきてる部分でもある。元の決まったかたちはないし、曲という素材をどういう風にライヴで演じていくかということだからね。その時代に合う、そのときに感じることをやるしかないんですよ。  ──じゃあこの辺で、ひとつ提案を。第一弾のときにスカートは「オートバイ」を直枝さんを迎えて一緒にカヴァーしましたが、YYGとしても何か考えていますか? 西田 じつは、ぼくは考えてるんですよ。 直枝 マジで! 西田 (2月のスカートを)見て、「うらやましいな!」って思ってたんで。それこそreddamがめちゃくちゃ選曲を練ってます。「なにかいい案ないかな」ってreddamに言ったら、いろいろ案を練りすぎちゃってて、もうぼくの理解の範疇を超えてました(笑) 吉田 いや、おれに内緒で練られても、言われないとわかんないから(笑) 西田 でも、絶対に何かやらせてもらいたいなと考えてます。 直枝 そこは無理のない範囲で(笑)。逆に、ぼくはセッションがしたいので、そこは提案します。一緒に歌ってもらえたら最高ですけど。 吉田 カーネーションをあらためて今回いろいろ聴かせてもらっていて、自分の中ではさっきも言ったようにウィルコ的な憧れの存在なんですけど、ウィルコにはなくてカーネーションにはあるという要素もあって。それは、基本的なスタイルが一個じゃないところなんですよね。強いスタイルが何個かある。 西田 わかる。 吉田 わかるよね。うちのバンドもファンキーな路線とフォーキーな路線とかいくつかあるんですけど、カーネーションも芯にあるスタイルが3つとか4つとかあって凄く参考になる。そういうバンドってめずらしいじゃないですか。「EDO RIVER」とか、パーカッションは入ってないけどいつでも入れられそうな「Shooting Star」とか。ぼくはそういうスタイルのコンポーズはできたことがないんで、コピーしたらすごく学ぶところがありそうだなと思ってました。なので、そういうところも含めてバンドのみんなと相談して決めたいと思ってます。 ──スカートの「オートバイ」にしても、じつはスカートの曲ってああいうループ感はほとんどないじゃないですか。そこをあえて生音でやってみたというのが、こういう場のおもしろさでもあると思って見てましたね。 直枝 あれはスカートがもっとも黒人音楽に近づいた瞬間でしたね(笑) 吉田 最近のジャズも、ループだったり、ヒップホップ感覚だったり、今までは混ぜられなかったものを混ぜてるじゃないですか。 直枝 ある意味で、編集による音楽だよね。 吉田 じつは、カーネーションの『天国と地獄』(1992年)もそういうところがあると思うんです。あらためてあの作品を聴いて、ぼくもあの時期に自分にも音楽を作る能力あったらブレイクビーツやってたと思いました(笑) 直枝 作曲の動機として一番いいのはリズムのループを組むことですから。 ──確かに、『天国と地獄』は90年代前後のヒップホップが一番サンプリングとか自由にやっていた時代の大胆な編集センスを取り入れた作品でもあるし、カーネーションにとってのひとつの分岐点でもありましたよね。 直枝 そうですね。黒人音楽というものをぼくは直接音楽的に取り入れようとはそれまでしてなかった。カーネーションに何が欠けてるかを考えたときに、もっと根底のリズムの作り方とかを学ばなきゃいけないと思った。リスナーとして反省したんです。それで、ラテン、レゲエ、ソウル、R&B、そういうものをたくさん聴きました。森高千里さんに曲提供をしたときの印税をほぼレコードに使いました(笑) 吉田 いい話ですね(笑)。でも、それでラテンの要素とかが音楽に入り出したというのはすごいです。 直枝 聴くことが勉強だと思って、一気に勉強したんです。 ──ずっとリスニングを続けていて、キャリアを経ても影響を受けてOKだっていう姿勢のアーティストのほうが、やっぱりおもしろいですよね。 直枝 ぼくはあの頃、30歳でした。29歳の時点で「何やってるんだ、おれは?」と落ち込んで、そこからまたすごくレコードを聴きはじめた。 吉田 お話を聞いてると、やっぱり参考になるなと具体的に思うところが多いんですよね。今直枝さんが言っていたような、あらたに吸収してアウトプットする回路は、自分たちにも理解できるものなんです。 西田 めっちゃわかる。「神秘的なものだから解き明かしたくない」という感じになっちゃう人がいるのもわかるんだけど、こっちは「神秘的なのはわかるけど、だからこそできるだけ解き明かそうよ」という気持ちがある。直枝さんのやってる音楽って、絶対にこっち側の感覚だとぼくは勝手に思ってて。それが接していてもめちゃめちゃ気楽なんですよ。自分たちもこうでありたいし、ずっとこういう風でいてくれる先輩がいるのは最高だな、って。 直枝 今、湯浅学さんと2ヶ月に一回〈アナログばか一代〉ってアナログ・レコードを聴くイベントをやってるのも、「聴く」ってことが一番重要だと思ってるから。聴いて、感じて、想像する。「これってもっと音よくなるよね」と探る。そこは作曲の根本にもあるから。その気持ちは忘れたくないと思うよね。年齢は関係ないよ。今気が付くということが重要なんで。 | |
 | |
| トップへ carnation-web | |